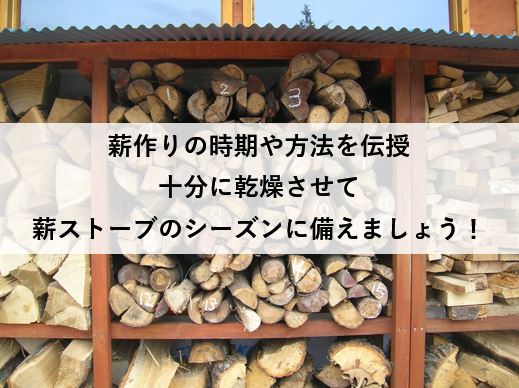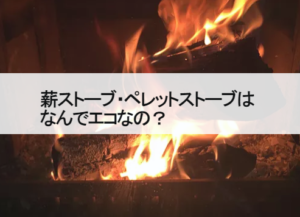薪ストーブの性能を100%引き出すための理想的な薪作りについてご紹介します。
初めて薪作りをする方はビックリするかと思いますが、表面の含水率15%程度の理想的な薪をつくるには、およそ2年間の歳月が必要です。
また、薪づくりはいつ開始してもよいものではありません。薪ストーブに適した木を使用する必要もあります。
効率よく理想的な乾燥度の薪を作るには、この樹木の水分量が一番少ない時期に伐採して、そして玉切り、薪割りといった作業が必要となってきます。
薪ストーブを快適に・安全に使用する為に、薪作りについて学んでいきましょう。
伐採期は水分量が少ない11月~12月 ( 1年目 )
11月~12月は、昔から樹木の伐採に適しているといわれている時期です。
特に12月中に伐採するのが理想的ですが、遅くとも1月までには伐採作業を終えるようにしておきましょう。
水分量の多い時期に伐採した薪は、乾燥するのに時間がかかることになりますので、この時期に伐採をしましょう。
伐採した木を原木と言います。乾燥していない状態なので、安く購入できます。
玉切り期1月~1月後半 (1年目 )
伐採した原木を、薪ストーブに適した長さに切りそろえることを玉切りといいます。お持ちの薪ストーブに入る薪の長さを事前に調べておきましょう。
薪割り期 玉切り後すぐ3月までに (1年目 )
玉切りした丸太は切断面「木口(こぐち)」から乾燥します。
その後、木部組織が硬化するため薪割り作業が難しくなりますので、玉切り作業を終えたらすぐに薪割り作業へと移行しましょう。
玉切りした木(丸太)を縦に割ります。
こうすることで乾燥しやすくなります。
薪割りは体力が要りますので、薪割り機があると便利です。
乾燥 雨よけ期 4月~10月 ( 1年目 )
薪を薪棚で保管します。
薪棚がまだない人は、①「真上からの雨を防ぐ」②「直接地面に薪を置かない」③「割った面を上にして積む」の3点に注意しましょう。
薪小屋を作るのがベストです。

これから約1年半乾燥させます。
薪作りを開始して2年目から
2年目は、適宜薪棚の前後を入れ替えて乾燥度合いを均一にしましょう。
うまくいけば10月ごろに完成です。
薪の表面の乾燥度を電気抵抗式水分計で測定していましょう。
表面の含水率15%程度でしたら理想的な薪と言えるでしょう。
最後に
いかがでしたでしょうか?
どうしても2年と聞くと長く感じますが、薪は水分量を25%以下にしないと煙がたくさん出てしまい室内では使えません。

ご自身で薪作りをする方は、薪ストーブの性能を100%引き出せるように頑張りましょう。
薪作りが面倒な方へ
薪ストーブ用の薪を作るには非常に労力がかかります。
薪ストーブは楽しみたいけど薪作りは面倒くさいと思う方は、購入をおすすめします。 那須高原プランニングでは薪ストーブに適した広葉樹の薪の販売を行っております。

薪の購入についての詳細はこちら
那須高原プランニング店舗情報
薪ストーブ・ペレットストーブに関する事は那須高原プランニングにお任せください。

那須高原プランニング有限会社
〒325-0303
栃木県那須郡那須町大字高久乙2730番地13
営業時間:9時~20時
TEL 0287-73-8581